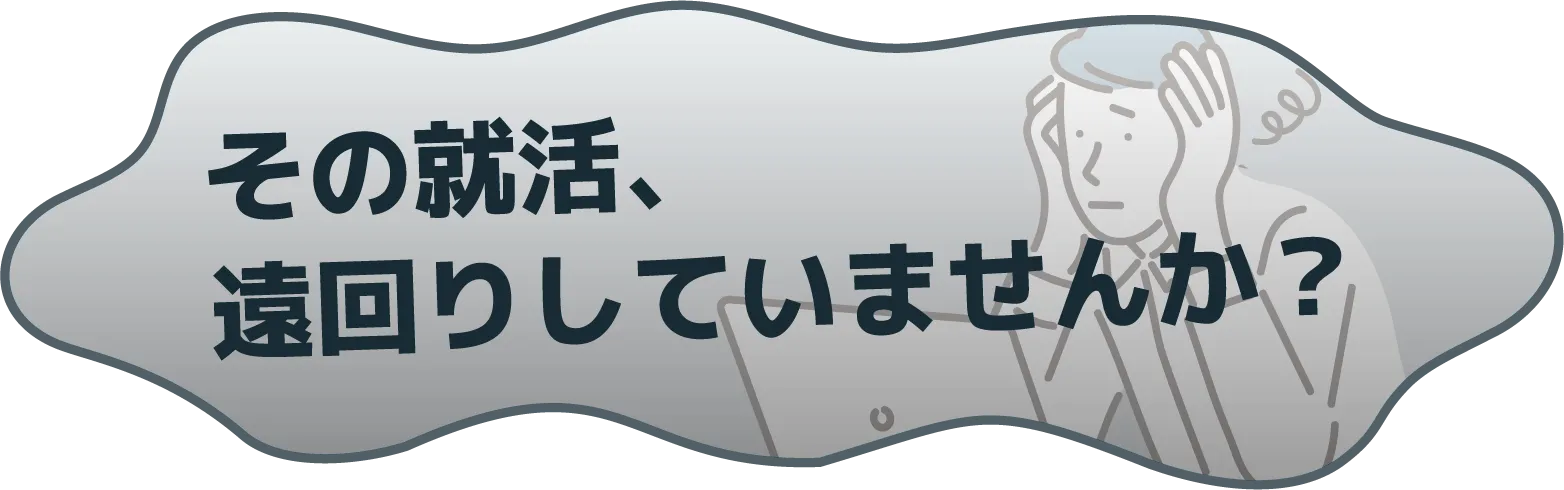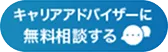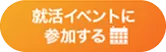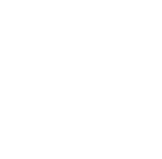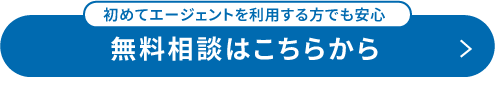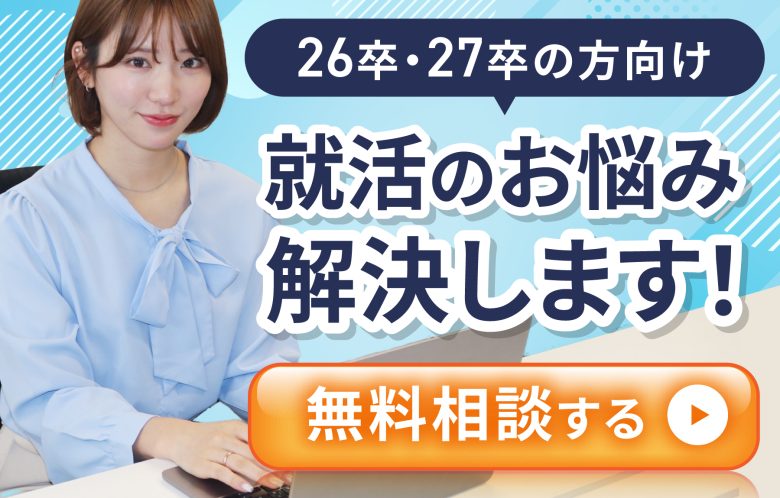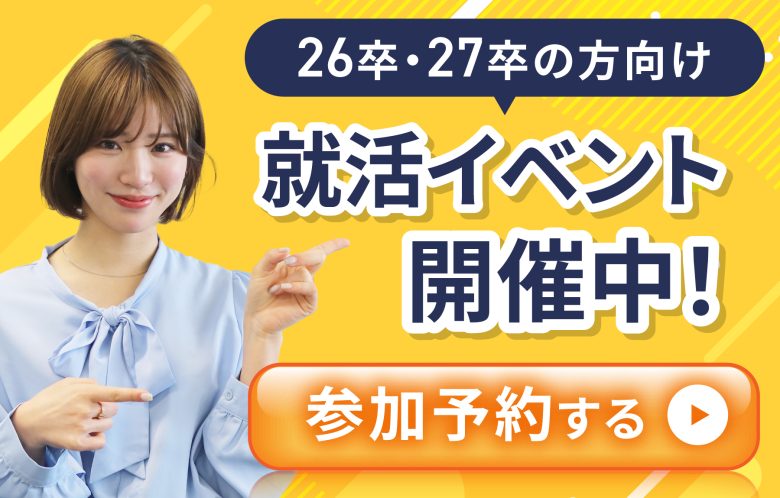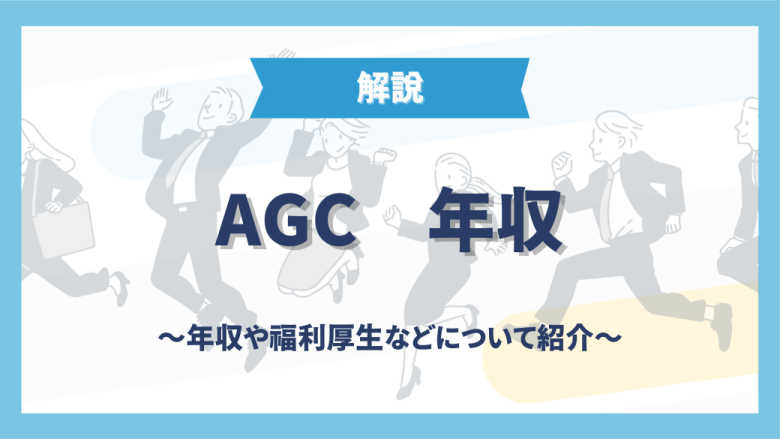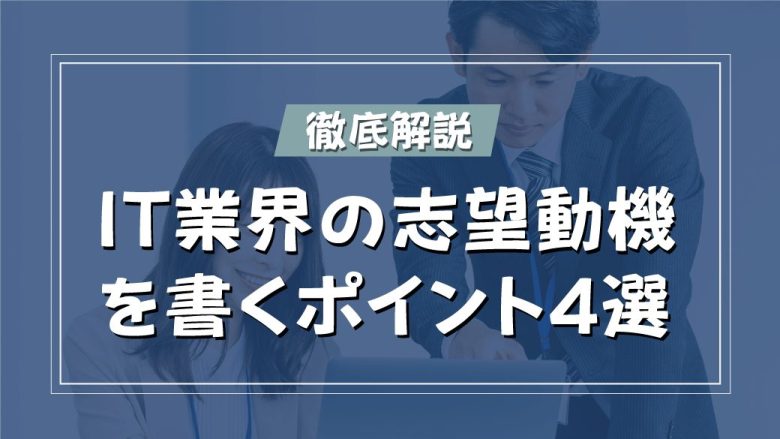良い仕事とは何か?意味や特徴・見つけ方を徹底解説!
2025.08.08 更新


監修者
熊谷 直紀
監修者熊谷 直紀
横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。
2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。
内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。
良い仕事とは何か、悩んでいませんか?「やりがいが欲しい」「本当にこの働き方で良いのか」といった不安を感じている方も多いでしょう。やりがいや収入、人間関係など、会社選びで重視するポイントは人それぞれです。
この記事では「良い仕事」の定義や、選び方、やめておいたほうがいい仕事の特徴までを、最新の公的データに基づき解説します。あなたにとっての“良い仕事”を見つけるヒントが見つかるはずです。
大手からベンチャーまで
内定獲得を徹底サポート!!
就活のプロであるキャリアアドバイザーが1対1で直接面談
 入社実績15,000名以上※1
入社実績15,000名以上※1 満足度94%※2
満足度94%※2 最短1週間内定※3
最短1週間内定※3

良い仕事とは何か?その定義と人による違い
ここでは「良い仕事とは何か」について、一般的に挙げられる条件や、就活生と社会人による捉え方の違い、そして明確な定義が存在しない理由について解説します。
「良い仕事」に共通する一般的な条件
「良い仕事」と感じるかどうかは人によって異なりますが、多くの人が共通して重視する要素も存在します。たとえば、適正な労働時間や安定した収入、仕事に対するやりがい、良好な人間関係、安心して働ける職場環境などが挙げられます。
また、成長の機会があることや、プライベートと両立しやすい働き方も、多くの労働者にとって重要な条件とされています。これらの要素は厚生労働省の推奨する職場づくりの基準にも沿っています。誰にとっても理想的な仕事を定義するのは難しいものの、一定の傾向はあるといえるでしょう。
出典:目指しませんか?「働きやすい・働きがいのある職場づくり」|厚生労働省
就活生や社会人が考える“良い仕事”の基準
「良い仕事」の基準は、年齢や経験、職業観によって変化します。たとえば、就職活動中の学生は、給与水準や福利厚生、企業の知名度や安定性など、客観的な条件を重視する傾向があります。
一方で、実際に働いた経験を持つ社会人は、職場での人間関係や裁量の広さ、仕事に対する達成感といった主観的な満足度を重要視するようになります。
こうした違いは、人生のステージや優先する価値観が変化することで自然に生じるものであり、「良い仕事」の定義が人によって異なる理由の一つといえるでしょう。働くうえで何を大切にしたいかを見つめ直すことが、より納得のいく仕事選びにつながります。
良い仕事に明確な定義がない理由と考え方
「良い仕事」に明確な定義が存在しないのは、働く人の価値観や状況が多様であるためです。たとえば、家族との時間を重視する人にとっては、残業が少なく休日が確保される職場が理想かもしれません。
一方で、スキルアップや昇進を重視する人にとっては、成長の機会が多く、挑戦的な環境のほうが魅力的に感じられます。また、同じ仕事でも、年齢や健康状態、生活環境の変化によって感じ方が変わることもあります。
こうした背景を踏まえると、画一的な定義を設けるのではなく、自分自身の価値観に照らし合わせて「良い仕事とは何か」を考える視点が求められます。個人の納得感を大切にしたキャリア設計こそが、持続的な働き方につながります。
良い仕事の5つの具体的な視点
ここでは「良い仕事」を見きわめるための5つの視点として、やりがい・給与・職場環境・将来性・安定性の観点から、それぞれの特徴と判断基準について解説します。
やりがいを感じる仕事の特徴とメリット
やりがいのある仕事とは、業務を通じて達成感や充実感を得られる仕事です。自分の役割が社会や他者の役に立っていると実感できたり、自分の得意分野や興味を活かせる内容であれば、仕事への意欲も自然と高まります。
やりがいを感じる仕事には、以下のような特徴が多く見られます。
- 社会的意義や貢献を感じられる(医療・教育・福祉分野など)
- 成果が目に見える形で現れやすい
- 自分のスキルや強みを活かして働ける
- 他者からの感謝やフィードバックを得やすい
こうした要素がある仕事では、努力が成果に結びつきやすく、自己効力感や成長実感を得る機会が多くなります。やりがいは数値で測れない要素ですが、日々の肯定的な経験の積み重ねが、働き続けるモチベーションにつながります。
出典:新しい時代の働き方に関する研究会 報告書 参考資料 | 厚生労働省
給与・待遇の良さが仕事満足度に与える影響
給与や待遇は、生活の安定や将来の計画を支えるうえで欠かせない要素です。たとえやりがいを感じる仕事であっても、報酬が業務内容や責任に見合っていなければ、不満や離職の原因となる可能性があります。
厚生労働省が公表した「令和5年雇用動向調査結果」によると、自己都合離職者の離職理由のうち「収入が少なかった」と回答した30~34歳の男性は14.1%を占めており、待遇への不満が離職の一因となっていることがわかります。さらに昇給や賞与、福利厚生などの水準も、仕事への継続意欲や心理的な安心感に直結します。
待遇面が整っている職場では、経済的な不安が少なく、長く働き続けるための基盤が築かれやすくなります。
出典:厚生労働省が公表した「令和5年雇用動向調査結果」
働きやすい職場環境とワークライフバランス
働きやすい職場とは、心身ともに無理なく安心して働ける環境が整っていることを指します。たとえば、長時間労働が常態化していないことや、有給休暇が取得しやすい雰囲気、上司や同僚との信頼関係があることなどが挙げられます。特に以下のような制度や文化が整っている職場は、働きやすさの観点からも評価されやすい傾向にあります。
風通しの良い職場や柔軟な勤務制度が整うことで、ワークライフバランスが向上します。結果として、仕事のパフォーマンスや継続意欲の向上にも好影響を与えます。
出典:第2節 テレワーク活用のメリットについて|厚生労働省
出典:育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省
出典:NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント|政府広報オンライン
出典:いきいき職場づくりのための参加型職場環境改善の手引き|厚生労働省
将来性のある仕事の見分け方
将来性のある仕事とは、今後も安定した需要が見込まれ、技術革新などの変化にも対応できる柔軟性を持つ職種を指します。たとえば、介護・医療・IT・再生可能エネルギーなどの分野は、社会的な課題やニーズの拡大に伴い、人材需要が増加しています。
また、AIや自動化の進展によって影響を受けにくい業務かどうかも判断材料になります。加えて、業務を通じて新たなスキルが身につくか、他職種にも応用できる知識を得られるかも重要です。
短期的な人気ではなく、中長期的に安定したキャリアを築けるかどうかの視点で職種を選ぶことが求められます。
出典:「IT・デジタル人材の労働市場に関する研究調査事業」調査報告書|厚生労働省
出典:IoT・ビッグデータ・AI等が雇用・労働に与える影響に関する研究会 報告書|厚生労働省
安定性・雇用の安心感を得られる仕事とは
安定性のある仕事とは、経済の変化や社会状況の影響を受けにくく、雇用が比較的守られやすい仕事を指します。代表例としては、公務員、ライフラインを支えるインフラ関連職、医療や介護などの福祉分野が挙げられます。
また、企業規模だけでなく、内部統制や経営基盤の強さ、柔軟な働き方への対応状況なども、安定性を判断するうえでの材料となります。
さらに、労働契約の安定性や職場内の人間関係、離職率の低さなども、安心して働き続けられるかどうかの重要な指標です。短期的な印象にとらわれず、企業の公開情報などを活用して見きわめる視点が求められます。
自分に合った良い仕事を見つける3ステップ|会社選びの基本

良い仕事に就くためには、自分に合った職場や働き方を見きわめることが大切です。そのためには、「自己理解」「企業理解」「選択の基準」を段階的に整理する必要があります。ここでは、納得感のある仕事選びを実現するために役立つ3つのステップについて、具体的な進め方を紹介します。
ステップ1 自己分析で仕事観・強みを把握する
最初のステップは、自分の「仕事観」や「価値観」、そして「強み・適性」を明確にすることです。仕事観とは、働くうえで何を大切にしたいかを示す考え方で、「安定性」「やりがい」「人との関わり」などが代表例です。
強みを整理する際は、以下のような視点が有効です。
- 成果を出せた経験の背景や理由
- 他人からよく褒められた点
- 自分が無理なく継続できた行動や習慣
- 役割を担った際に自然と力を発揮できた場面
こうした自己分析は、職種や業界の選定だけでなく、面接での自己PRにもつながります。リクナビやマイナビといった就職支援サイトでは、無料の適性診断ツールも活用できます。自分自身への理解を深めることが、良い仕事に出会う第一歩となります。
ステップ2 企業研究で実態を把握する方法
自己理解を深めた後は、企業研究によって働く環境や制度の実態を把握しましょう。企業研究では、仕事内容のほか、企業の規模、成長性、働き方、福利厚生、社風などを多面的に調べることが重要です。
以下は、主な調査項目とその情報源の例です。
| 調査項目 | 情報源の例 |
|---|---|
| 仕事内容・事業内容 | 企業公式サイト、採用情報ページ、有価証券報告書 |
| 福利厚生・制度 | 求人票、就活ナビ、合同説明会 |
| 社風・人間関係 | OB・OG訪問、口コミサイト、インターンシップ |
| 将来性・安定性 | IR情報、業界ニュース、厚生労働省・経産省の統計 |
表面的なイメージにとらわれず、実際の職場環境やキャリアパスと自分の価値観が一致するかを確認しておきましょう。現場の声を聞く機会も積極的に活用しましょう。
ステップ3 条件に優先順位をつけて選択する
最後のステップは、自分が仕事に求める条件を整理し、優先順位を明確にすることです。すべての希望を満たす仕事を見つけるのは難しいため、「絶対に譲れない条件」「できれば満たしたい条件」「妥協できる条件」に分けて考えると整理しやすくなります。
たとえば、勤務地、勤務時間、給与水準、福利厚生、社風、キャリア形成のしやすさなどが判断基準となります。このプロセスを通じて、自分の働き方に対する価値観がより具体的に見えてくるでしょう。
求人票の情報だけでなく、説明会やインターンシップなどの実体験を通じて比較・検討することが、後悔の少ない選択につながります。
良い仕事を判断するための情報収集術
良い仕事に出会うためには、企業の表面的なイメージではなく、実態に即した情報を多面的に収集することが重要です。ここでは、企業の公式情報や口コミ、OB・OG訪問、インターン、説明会、診断ツールなどを活用し、自分に合った職場を見きわめるための具体的な手法を解説します。
企業HP・口コミ・OB訪問を活用する方法
企業研究の出発点として、企業の公式サイトを活用しましょう。採用情報や事業内容、企業理念、福利厚生、働き方などが掲載されており、一次情報として信頼性が高い特徴があります。
加えて、口コミサイト(例:OpenWork)では、現役社員や退職者による評価を通じて、職場の雰囲気や実際の勤務状況を把握できます。さらに、OB・OG訪問では、個別の実体験に基づいた情報が得られ、自分の志向と照らして検討しやすくなります。
こうした複数の情報源を活用し、企業の公式な姿と現場の実態をバランスよく比較することで、より正確な判断につながります。
インターンや説明会で得られるリアルな情報
企業説明会やインターンシップは、公式情報では伝わりにくい職場のリアルを体感できる重要な機会です。
とくにインターンでは、実際の業務や社員とのやりとりを通じて、企業文化やチームの雰囲気、職場の働きやすさを肌で感じられます。
説明会では人事担当者と直接対話できるうえ、他の参加者の質問からも新たな視点を得られる可能性があります。説明内容だけでなく、担当者の対応の丁寧さや熱意も、企業の社風を読み解く手がかりになります。
自ら参加し、五感で得た情報を基に判断することが、ミスマッチを防ぐ第一歩になります。
自己分析にオススメの診断ツール(適職診断・性格診断など)
適職診断や性格診断などのツールは、自己分析を深めるうえで有効な手段です。こうしたツールは、簡単な質問に答えるだけで性格の傾向や職業適性を客観的に可視化でき、就職活動の初期段階で役立ちます。たとえば大学提供の「適職診断」や、
「16Personalities」などの無料サービスは、多くの求職者に活用されています。ただし、診断結果はあくまで参考情報にすぎません。結果に一喜一憂するのではなく、キーワードや傾向を手がかりに、自分の価値観や希望する働き方と照らし合わせて考える姿勢が大切です。
良い仕事に就くために知っておきたい選考対策
就職や転職で「良い仕事」に就くためには、単に条件の良い求人に応募するだけでは十分とは言えません。選考を突破するには、自己理解や企業理解に基づいた事前準備を通じて、自分と企業との適合性を明確に伝える必要があります。
ここでは、選考前に押さえておきたい準備や、評価されやすい価値観の伝え方について解説します。
良い仕事に就く人が意識している準備とは
良い仕事に就いている人の多くは、選考に向けた事前準備を丁寧に行っています。中でも重要なのが、自己分析と企業研究です。
自己分析では、これまでの経験や価値観を振り返り、自分がどのような働き方を重視するのかを明確にします。
企業研究では、その企業の理念や職場環境が自分の価値観と合致しているかを見きわめ、志望理由との整合性を強めるのがポイントです。
また、OB訪問や会社説明会への参加を通じて、実際の雰囲気を知ることも大切です。こうした行動は、選考時に「本気度」や「マッチ度」の高い印象を与え、自分らしい言葉で説得力あるアピールにつながります。
企業から評価される「価値観」とは?
企業が採用で重視するのは、単なるスキルや実績だけでなく、その人が持つ「価値観」と企業の文化が合致しているかどうかです。
たとえば、チームワークを大切にする、自発的に課題解決に取り組む、成長意欲を持って挑戦するなどの価値観は、多くの企業において高く評価される傾向があります。なぜなら、価値観が企業文化と合っている人ほど、入社後の定着率や活躍が期待できるからです。
応募先企業の理念や行動指針と自分の価値観を照らし合わせ、共通点を見つけることが大切です。自己分析を通じて得た価値観を選考の場で自然に伝えることで、企業との相性の良さをアピールできます。
自己PR・志望動機に仕事観を反映させるコツ
自己PRや志望動機に自分の仕事観を反映させる際は、以下の3点を意識しましょう。
- 【具体性】抽象的な価値観ではなく、経験に基づいて語る(例「○○体験から△△を学び」)。
- 【共通点の提示】応募先企業の理念や事業内容とあなたの価値観がどう重なるかを明示する。
- 【背景の明示】なぜその仕事観が形づくられたのか、背景や心理の変化も伝える。
一貫性と説得力ある志望動機の作成が可能になり、採用担当者の理解も深まります。
良い仕事をする人の特徴と習慣

良い仕事を継続するには、成果を出すだけでは不十分です。日々の業務で、自身の姿勢や習慣が仕事の質を左右します。ここでは、そうした人物が共通して持つ思考や行動の特徴を解説します。
良い仕事をする人に共通する思考と行動
良い仕事をする人は、常に「目的意識」と「改善思考」を持って行動しています。業務に対して「なぜこの作業を行うのか」と問い直すことで、無駄を省き、効率的な判断が可能になります。
また、現状に満足せず、「もっと良くするにはどうすべきか」と考える姿勢も欠かせません。さらに、報告・連絡・相談(報連相)を徹底し、チームとの連携を密に保つことも特徴です。
このような積極的かつ協調的な行動が、仕事の質の向上と信頼獲得につながります。
【行動特性】
- 業務の目的を常に意識する
- 現状を見直し、改善策を考える
- 報連相をこまめに行い、連携を強化する
- 業務全体を俯瞰して優先順位を立てる
職場で信頼される人の働き方とは
信頼される人は、成果だけでなく日々の態度や他者への配慮でも高く評価されます。具体的には、納期を守る、丁寧な言葉遣いをする、他者の立場に配慮して行動するなど、基本を確実に実践することが重要だと言えるでしょう。
問題が起きたときも責任転嫁せず、自ら対応する姿勢が信頼構築の礎になります。加えて、感情の起伏を抑えて安定した対応ができる人は、周囲に安心感を与え、自然と協働が生まれます。
信頼は一朝一夕では得られないため、日々の誠実な積み重ねが鍵を握ります。
成果を出す人が大切にしている「単純作業の積み重ね」
成果を出す人ほど、華やかなスキルよりも「地道な作業の継続」を重視しています。たとえば、毎日のタスク整理、迅速なメール返信、資料やファイルの整頓など、一見地味な作業を丁寧にこなすことが、全体の業務効率を支える基盤となります。
これらを疎かにすると、ミスの発生や時間の浪費につながるため、基本を徹底する姿勢が求められます。日々の単純作業をルーティンとして確立し、それを習慣化することが、長期的な成果や信頼につながるのです。
【ルーティン作業例】
- 毎朝のタスク整理と優先順位の確認
- メール・チャットへの迅速かつ丁寧な対応
- ファイル・資料の整理整頓
- 一日の振り返りと翌日の準備
良い仕事に就くために必要な考え方と行動
理想の仕事に出会うためには、求人情報を見るだけでは不十分です。日々の思考の持ち方や行動習慣が、最終的な仕事選びに大きな影響を与えます。ここでは、良い仕事に就くために重要なマインドセットや具体的な行動、そしてグローバル化に伴い需要が高まっている英語力の活用方法について解説します。
良い仕事に出会うために必要なマインドセット
良い仕事を得ている人には、共通する思考傾向があります。それは「選ばれることを待つのではなく、自ら選ぶ」という主体的な姿勢です。
将来のキャリアを見据えた長期的な視点を持ち、変化を恐れず柔軟に対応できることも大切です。失敗を学びに変える姿勢や、自分自身を客観的に理解しようとする努力が、より深い自己理解につながります。
また、理想だけに囚われず、現実とのバランスを取りながら進む柔軟な考え方も必要です。このようなマインドセットは、良い仕事との出会いを引き寄せる土台となります。
チャンスをつかむ人が意識している行動習慣
良い仕事に就く人は、日々の小さな努力を継続しています。情報収集、ネットワーキング、スキルアップなど、見えない部分での積み重ねが、いざという時の差になります。好機を逃さないためには、「今できること」にアンテナを張る姿勢が必要です。
チャンスをつかむ人の行動パターン
| 行動習慣 | 目的・効果 |
|---|---|
| 就活ナビサイト・企業HPを定期確認 | 情報鮮度を維持し、好機を逃さない |
| オンライン説明会・勉強会への参加 | 最新動向を知り、人脈構築にもつながる |
| キャリアセンターの活用 | 客観視と助言を得て、判断精度を高める |
| スキル学習・資格取得 | 競争力を高め、選択肢を広げる |
| 自己分析の定期的な更新 | 志望動機の一貫性と納得感を強化する |
「良い仕事に就く英語力」の重要性と学習法
近年では、グローバル化に伴い、英語力の有無が仕事の選択肢を左右する場面が増えています。特に外資系企業やグローバル展開を行う企業では、TOEICスコアの提出が求められたり、英会話スキルが昇進要件となったりするケースもあります。
こうした企業では、日常的な読み書きだけでなく、会議や商談などでの発信力も重視されるため、継続的なトレーニングが欠かせません。学習法としては、英語ニュースを日課として視聴したり、オンライン英会話を利用して実践的なスキルを磨いたりする方法が有効です。
完璧を求める必要はありませんが、少しずつ自信をつけていくことが、結果としてより多くの「良い仕事」との出会いにつながっていきます。
良い仕事を選ぶ際に気をつけたい落とし穴

理想の仕事を見つけようとするあまり、見落としがちな「選び方の失敗」もあります。特に条件や他人の意見に引きずられることで、本来自分に合った選択を見誤ることも少なくありません。ここでは、良い仕事を選ぶ際に陥りやすい落とし穴とその回避法について解説します。
条件ばかりにとらわれすぎていないか?
ここでは、「条件先行型の仕事選び」が抱えるリスクについて解説します。
年収や勤務地、残業の有無など、目に見える条件だけで仕事を選ぶと、入社後に「想像と違った」と感じるリスクがあります。たとえば、待遇は良くても人間関係が悪い、やりがいを感じられないといったケースです。
条件は一時的な満足につながっても、長期的な幸福とは必ずしも一致しません。大切なのは、自分の価値観やキャリアの方向性と照らし合わせて「本当に合っているか」を見きわめること。
条件を軸にするだけでなく、企業の文化や仕事内容、成長機会なども含めて総合的に判断しましょう。
他人の意見に流されすぎるリスク
ここでは、「他人軸での仕事選び」がもたらすリスクについて解説します。
家族や友人、SNSの声に影響されて仕事を選ぶ人は少なくありません。しかし、他人の価値観で判断してしまうと、いざ働き始めたときにモチベーションが続かない、やりがいを感じにくいなどの問題が生じます。
他人の意見はあくまで参考情報にすぎません。最も重視すべきなのは、自分がどんな環境で働きたいか、どのように成長したいかという内面の基準です。
迷ったときは、「この選択は自分自身が納得できているか?」を問い直すことで、後悔の少ない決断ができます。
「全部揃った仕事」を探して迷子にならない方法
ここでは、「完璧な仕事」を探し続けることで陥る落とし穴と対処法について解説します。
給与、勤務地、人間関係、やりがい、成長性……。すべてを兼ね備えた理想の仕事があれば魅力的に思えますが、実際にはすべての条件を満たす仕事はほとんど存在しません。完璧さを追い求めるあまり、選択肢を絞れず、就職活動が長引いてしまうこともあります。
重要なのは、「自分が何を最も大切にしたいか」を明確にすること。すべてを満たすのではなく、優先順位を決めて“譲れない条件”に絞り込むことで、現実的かつ納得感のある選択が可能になります。迷子にならないためにも、現実とのバランスを意識しましょう。
まとめ

「良い仕事」とは、誰にとっても共通の正解があるものではなく、自分自身の価値観やライフステージ、働き方の希望に応じて定義が変わるものです。
やりがいや給与、職場環境、将来性、安定性といった視点から、自分にとって何が最も大切かを整理し、優先順位を明確にすることが重要だと言えるでしょう。そのうえで、自己分析や企業研究を通じてミスマッチを防ぎ、自分らしく働ける環境を見きわめましょう。
また、選考対策や日々の行動習慣も、良い仕事との出会いにつながります。迷ったときは、「自分が納得して選べるかどうか」という視点を大切に。焦らず一歩ずつ、自分にとっての“良い仕事”を見つけていきましょう。
よくある質問
Q. 「やりがい」と「安定」どちらを優先すべき?
自分の価値観やライフステージに応じて優先順位を決めましょう。
若いうちは「やりがい」を重視し、成長できる環境を選ぶのも一つの手です。生活の安定が重要な時期には「安定」を重視する選択も合理的です。
Q. やりたい仕事がないときはどうしたら良い?
まずは「やりたくないこと」から絞り、行動しながら探すのがおすすめです。
完全な正解を求めず、自己分析や現場体験を通じて選択肢を広げましょう。動くことで見えてくるものも多くあります。
Q. 診断で向いていない職種が志望職種だったら?
診断結果は参考程度にして、自分の意思を優先しましょう。
なぜその結果が出たのかを分析することが、志望動機や強みの明確化に役立ちます。可能性を狭めないようにしましょう。
Q. 良い仕事とはどんな仕事ですか?
自分の価値観に合い、前向きに長く続けられる仕事です。
高収入や安定などの条件も重要ですが、自分が仕事に何を求めるかを明確にする必要があります。
Q. 食いっぱぐれない職業は?
インフラ系・医療・ITなど、社会的需要が高い職業です。
介護福祉士、看護師、電気・ガス関連、物流管理、ITインフラエンジニアなどが該当します。景気に左右されにくい分野です。
Q. やめたほうがいい職場の特徴は?
離職率が高い、慢性的な長時間労働、ハラスメント体質などは要注意です。
口コミサイトや社員インタビュー、面接時の対応などで職場の雰囲気を見極めましょう。誠実な説明のない企業には注意が必要です。