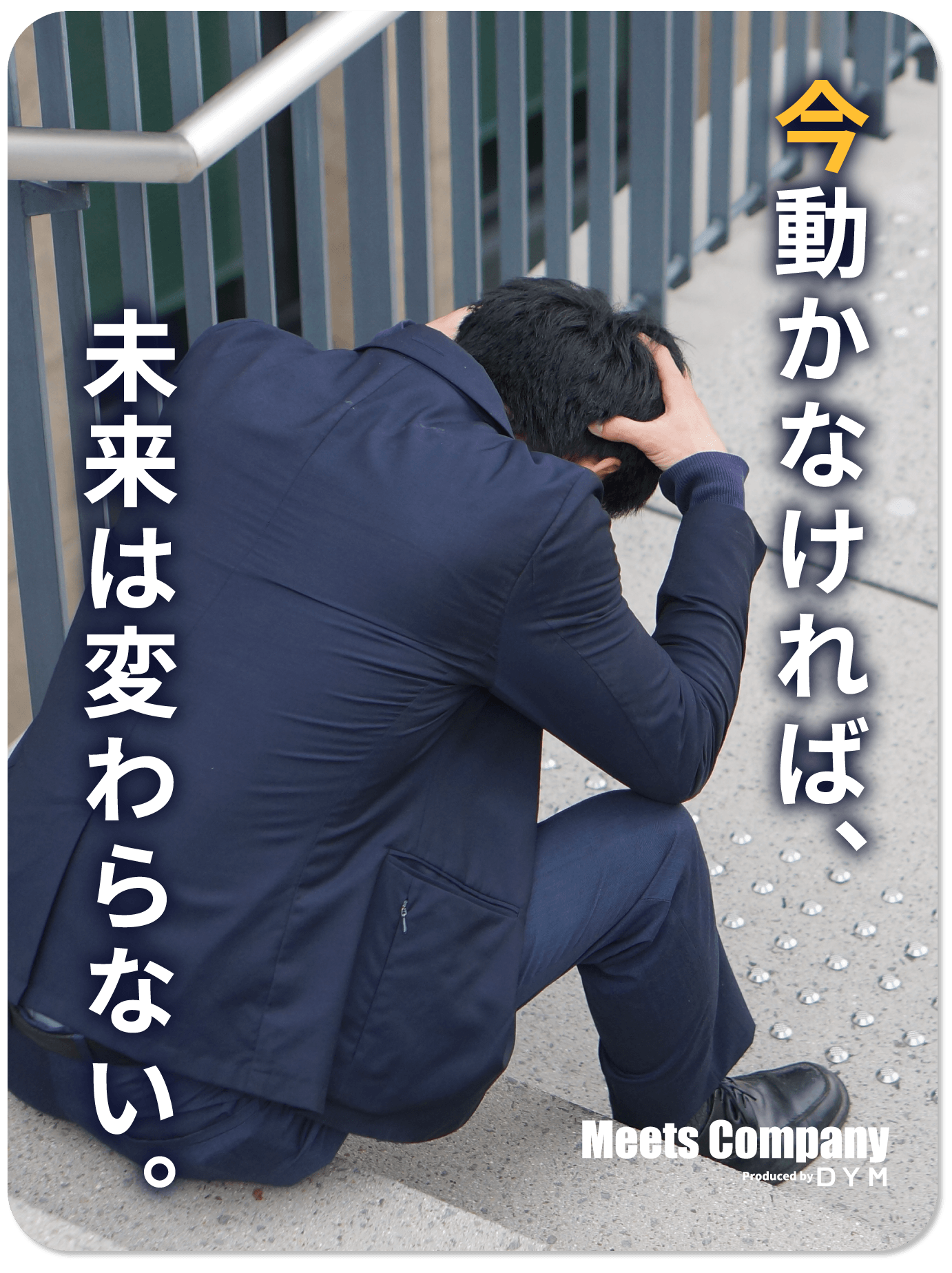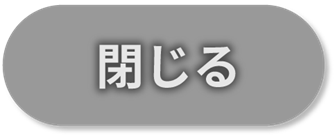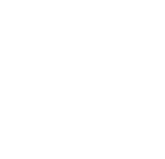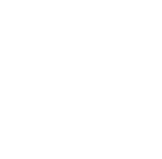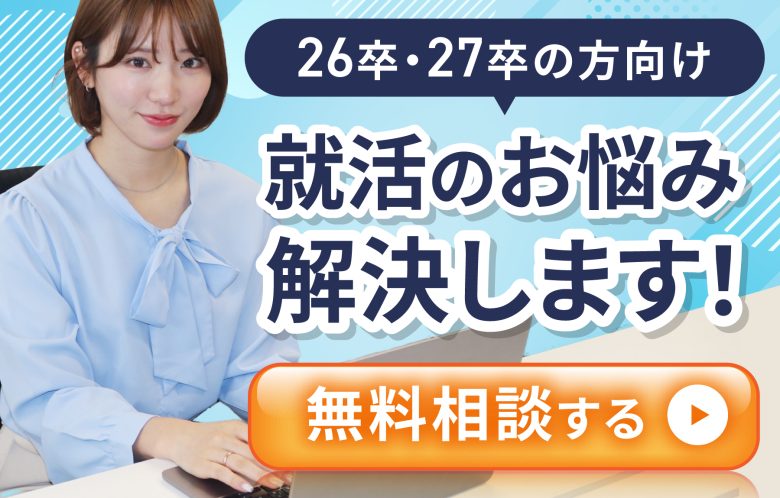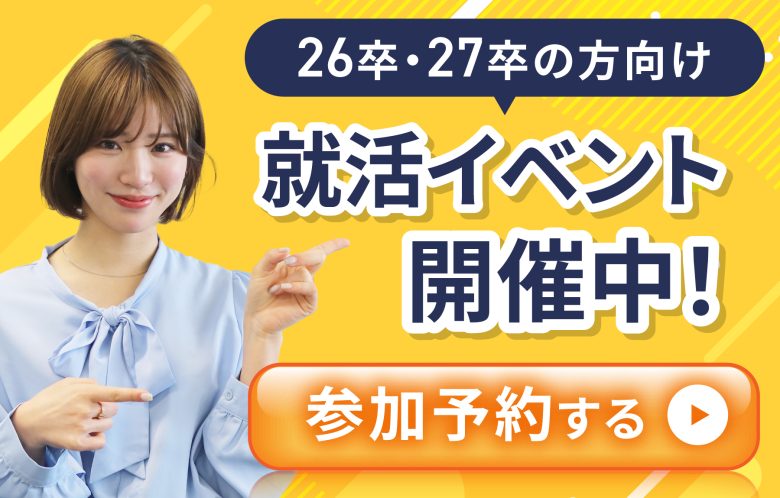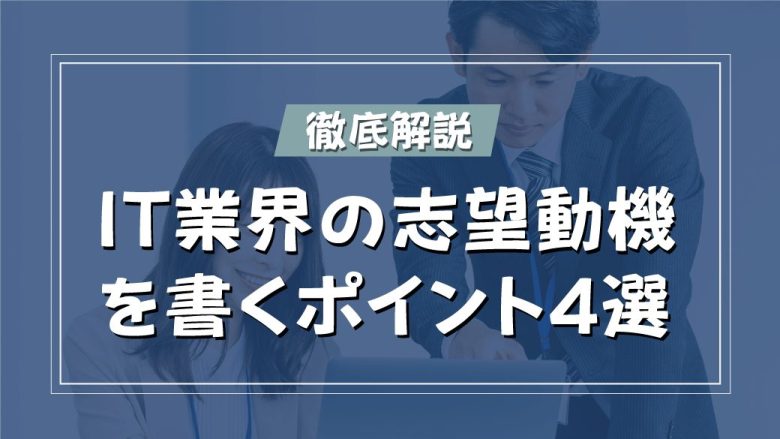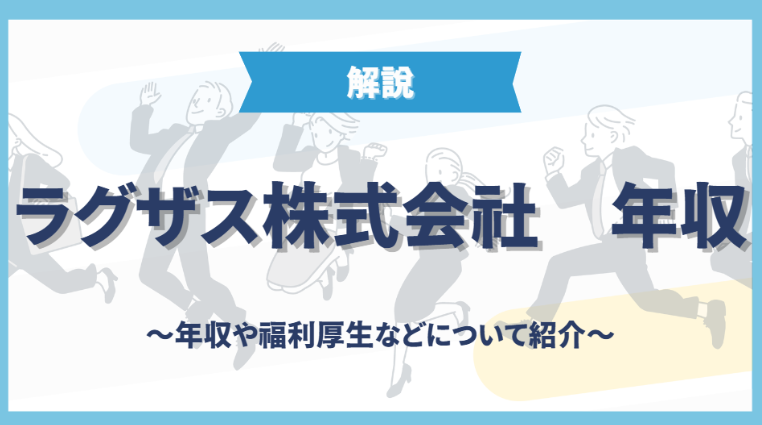モチベーショングラフの作成法を徹底解説!これで自己分析が変わる
2025.08.22 更新


監修者
熊谷 直紀
監修者熊谷 直紀
横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。
2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。
内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。
モチベーショングラフ対策として、本記事では「モチベーショングラフとは何か」「どのように作成し、自己分析や就職活動に活用できるのか」を解説します。主に就職活動中の学生や、自己分析を深めたい方を対象に、モチベーショングラフの基本概念や作成の手順、活用メリットをわかりやすく紹介します。自分の価値観や強みを明確にしたい方に役立つ内容です。
「モチベーショングラフって本当に自己分析に役立つの?」「どんな場面で作成すれば効果的なのか知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。モチベーショングラフは、幼少期から現在までのモチベーションの変化をグラフ化します。過去の出来事や感情の起伏を可視化する自己分析の手法です。これにより、自分がどのような状況でモチベーションが高まるのか、逆にモチベーションが下がるのはどんな時かを客観的に把握できます。こうした状況で、就職活動やキャリア選択で自分の強みや価値観の伝え方に悩む方、また面接で話すエピソードが思い浮かばない方にとって、モチベーショングラフは有効なツールとなるでしょう。

モチベーショングラフとは?

モチベーショングラフの基本概念や必要性、自己分析における重要性について解説します。過去の出来事とモチベーションの変化を可視化することで、自分の価値観や強みを理解する手法の概要を紹介します。
モチベーショングラフの基本概念
モチベーショングラフとは、自分の人生におけるモチベーションの変化を視覚的に表現するための自己分析ツールです。このグラフは、横軸に「時間(年齢や学年)」、縦軸に「モチベーションの高さ」を設定し、過去から現在までの出来事や感情の起伏を点と線でつなぐことで、自分の心の動きを一目で確認できるようにします。
モチベーショングラフは、単なる過去の出来事の羅列ではなく、自分の心の動きや価値観の変化を客観的に捉えるためのツールです。これにより、自分の成長過程や性格の傾向、モチベーションの源泉を深く理解することができます。また、グラフを通じて、自分がどんな環境・出来事に強く反応するのか、どんなときに力を発揮しやすいのかも見えてきます。
モチベーショングラフの必要性とメリット
自己理解を深める意義
モチベーショングラフを作成することには、自己理解を深めるための大きな意義があります。自分がどんなときにやりがいや充実感を感じるのか、逆にどんなことでやる気を失うのかを明確にすることで、自分のモチベーションの源泉や価値観を把握できるようになります。
就職・転職活動での活用メリット
就職活動や転職活動では、自己PRや志望動機を考える際に「自分が何を大切にしているのか」「どんな環境で力を発揮できるのか」を明確に伝えることが重要です。モチベーショングラフを使うことで、自分の強みや弱み、働きがいを感じるポイントを言語化しやすくなります。たとえば、チームで協力して目標を達成した経験や、困難を乗り越えた経験など、モチベーションが高まった出来事を具体的に挙げ、その理由や学びを説明できるようになります。
価値観や働きがいの振り返り
モチベーショングラフは、自分の価値観や働きがいを振り返るきっかけにもなります。グラフの山や谷となった出来事を分析することで、「自分がどんな環境や役割を求めているのか」「どんな課題に取り組みたいのか」が見えてきます。これにより、志望企業や職種選びの基準が明確になり、ミスマッチによる早期離職のリスクも減らせます。
弱みへの気づきと成長へのヒント
自己分析を深めるための手法として、モチベーショングラフは大きな価値を持ちます。単なる過去の振り返りではなく、人生の中でモチベーションが高まった瞬間や低下した場面を可視化することで、自分の価値観や強み・弱みを客観的に把握できます。このグラフを作成することで、どのような環境や出来事が自分のやる気を引き出すのか、逆にどんな状況で力を発揮しにくいのかが明確になり、仕事や企業選びの軸を定めやすくなります。
また、モチベーショングラフで得た気づきは、自己PRや志望動機を作成する際にも役立ちます。面接でよくある質問への具体的なエピソードとして活用でき、説得力のある自己表現につながります。さらに、自分の成長や変化を振り返ることで、今後のキャリア形成や新たな目標設定にも活用できる点が大きなメリットです。
モチベーショングラフの作成方法

モチベーションの変化を記録する具体的なステップや、横軸・縦軸の設定方法、エピソードの挿入方法、Excelを使った作成手順についてわかりやすく解説します。
モチベーションの変化を記録するステップ
印象的な出来事をリストアップする
モチベーショングラフを作成する際、まず重要なのは「モチベーションの変化を記録する」ステップです。この工程では、自分の人生のなかで印象深かった出来事や、感情が大きく動いたポイントを洗い出すことから始めます。
具体的には、幼少期から現在に至るまで、学年や年齢ごとに区切りをつけ、その時期に起こった大きな出来事をリストアップしていきます。小学校の運動会でリレーの選手に選ばれたこと、中学時代の部活動での挫折や成功、高校や大学での進路選択、アルバイトやインターンでの経験など、自分にとって記憶に残っている出来事を幅広くピックアップします。
モチベーションの高さを数値化する
次に、それぞれの出来事に対して、その時の「モチベーションの高さ」を直感的に数値化します。一般的には、やる気が最高に高まった瞬間を「10」、やる気が全く出なかったときを「0」とする10段階評価がわかりやすく推奨されます。
数値化することで、自分の感情や行動を客観的に振り返ることができ、より正確な自己分析につながります。この段階では、出来事の詳細だけでなく、その時の感情や考え方、行動もできるだけ具体的に書き出しておくと、後でグラフに反映させやすくなります。
感情や考え方も具体的に記録
この「記録する」ステップは、単なる出来事の羅列ではなく、自分の心の動きや価値観の変化を深く理解するための土台となります。そのため、思い出すのが難しい時期や出来事があっても、無理にすべてを網羅する必要はありません。
まずは印象に残っている出来事から始め、徐々に細かくしていくのがコツです。また、家族や友人に当時のことを聞いてみるのも、記憶を掘り起こす有効な方法です。最終的に、グラフ作成の材料として、出来事・感情・モチベーション数値のセットができる状態にします。
記録の積み重ねが自己理解の土台に
このようにして、自分の人生を振り返りながら、モチベーションの変化を丁寧に記録していくことで、自分がどんなときに力が出せるのか、どんなことでやる気を失いやすいのかが見えてきます。このプロセスは、自己理解を深めるだけでなく、就職活動やキャリア形成においても大きな武器となります。
横軸と縦軸の設定方法
横軸の設定:時間の流れを明確に
モチベーショングラフを作成する際、グラフの枠組みとなる「横軸」と「縦軸」の設定は非常に重要です。まず、横軸には「時間」を設定します。一般的には、誕生から現在までの年齢を1歳刻みや5年ごと、あるいは小学校・中学校・高校・大学など、区切りやすい単位で設定します。たとえば、0歳から現在までの年齢を横軸に並べ、それぞれの年齢や時期に該当する出来事を対応させていきます。年齢が正確に思い出せない場合は、入学や卒業など大きなイベントを基準にしても問題ありません。
縦軸の設定:モチベーションの高さを数値化
次に、縦軸には「モチベーションの高さ」を設定します。モチベーションの高さは、上をプラス(やる気が高い・充実感が強い)、下をマイナス(やる気が低い・落ち込んでいる)として、0から100、または-100から100などの幅で表現するのが一般的です。100が「最高にやる気がある状態」、-100が「最もやる気が出ない状態」とし、その中間を適切に配分します。このように数値化することで、モチベーションの変化を視覚的・定量的に捉えることができます。
作成方法とツールの活用
グラフの枠組みを作る際は、紙に手書きで線を引いてもよいですし、Excelやスプレッドシート、PowerPointなどのデジタルツールを使うとより簡単に作成できます。特にデジタルツールを使う場合、横軸の目盛りや縦軸の数値を自由に調整できるため、後から修正や追加もしやすくなります。
設定のポイント
縦軸と横軸の数値は必ずしも厳密なスケールでなくても構いません。自分の感覚に合わせて、モチベーションが高かった時期や低かった時期を明確に区別できるように設定することが大切です。
この「横軸と縦軸の設定」は、モチベーショングラフの基礎となる部分です。正しく設定することで、自分の人生の流れとモチベーションの変化が一目でわかるようになり、自己分析の精度が大きく向上します。
具体的なエピソードの挿入方法
出来事をグラフ上に配置する
モチベーショングラフを作成する際、単にグラフ上に点を打つだけでなく、具体的なエピソードや感情、行動を詳細に記録することが重要です。まず、先にリストアップした出来事を、横軸の該当する時期に合わせてグラフ上に点として配置します。この時、縦軸のモチベーション数値も同時に反映させ、その出来事が自分にとってどのくらいのインパクトがあったかを可視化します。
感情や行動を具体的に記録する
次に、各出来事の点の近くに、その時の感情や考え方、実際にどのような行動をとったのかをテキストや吹き出しで記入します。たとえば、「高校2年の時に部活動でキャプテンに選ばれ、責任感とやりがいを強く感じた」「大学2年の夏、インターンで初めて社会人と接し、自分の未熟さを痛感した」など、出来事と感情・行動をセットで記載します。この作業は、グラフを見返したときに、なぜモチベーションが上がったのか、下がったのかをすぐに理解できるようにするためのものです。
モチベーションの山・谷を深掘りする
また、モチベーションが大きく上下したポイントについては、特に詳細に記録するのがおすすめです。たとえば、挫折を経験した時期や、大きな目標を達成した時期など、自分の人生の転機となった出来事を中心に、その時の感情や考え方、学びを言語化しておきます。これにより、自分の強みや弱み、価値観が明確になり、自己分析の精度が高まります。
具体的なエピソードの記録が自己理解を深める
グラフにエピソードを挿入する際は、デジタルツール(ExcelやPowerPoint)の場合はテキストボックスや吹き出し機能を使うと便利です。紙に手書きの場合は、余白に直接書き込むか、付箋を貼って後から追加・修正できるようにしておくのもよいでしょう。このようにして、具体的なエピソードをグラフに反映させることで、自分の心の動きや成長過程をより深く理解できるようになります。
Excelを使ったグラフ作成の手法
Excelでのデータ入力とグラフ作成
Excelを使ったモチベーショングラフの作成は、手書きよりも修正や追加がしやすく、見栄えも良くなるためおすすめです。まず、Excelのワークシートを開き、A列に「年齢」や「時期」を設定します。たとえば、A1セルに「年齢」とタイトルを記入し、A2からA24まで0歳〜22歳の数字を割り振ります。次に、B列に「モチベーション数値」を入力します。B1セルに「モチベーション」と記入し、各年齢に対応するモチベーション数値をB2〜B24に入力します。
折れ線グラフや散布図の挿入
次に、A列とB列のデータを選択し、Excelの「挿入」タブから「折れ線グラフ」や「散布図」を選択してグラフを作成します。これにより、横軸に年齢、縦軸にモチベーションの高さが反映されたグラフが自動的に生成されます。グラフが作成できたら、各点にマウスを合わせて右クリックし、「データラベル」を追加することで、年齢やモチベーション数値をグラフ上に表示できます。
データラベルやエピソードの追加
さらに、グラフ上の各点にテキストボックスを挿入し、その時期に起こった出来事や感情、行動を記入します。Excelの「挿入」タブから「図形」を選択し、吹き出しやテキストボックスを追加して、具体的なエピソードを書き込むとわかりやすくなります。また、グラフのデザインや色、線の太さなども自由にカスタマイズできるため、見やすいグラフに仕上げることができます。
テンプレート活用で効率アップ
Excelを使うことで、データの修正や追加が簡単にできるだけでなく、グラフの見た目もプロフェッショナルに仕上がります。また、テンプレートを活用すれば、さらに効率的に作業を進めることができます。このようにして、Excelを活用したモチベーショングラフ作成は、自己分析をより深く、より効果的に行うための強力なツールとなります。
モチベーショングラフのテンプレートと作成ツール
無料で利用できるテンプレートや、おすすめのオンライン作成ツールを紹介し、効率的にモチベーショングラフを作成する方法を説明します。
無料でダウンロードできるテンプレートの紹介
モチベーショングラフの作成を効率化するために、さまざまな形式の無料テンプレートが複数のサイトで提供されています。テンプレートを活用すれば、グラフの枠組みや軸の設定を一から作る手間が省け、すぐに自己分析に取り掛かることができます。
Excel形式のテンプレート
Excel形式は、年齢や時期ごとにモチベーションの数値を入力するだけで、自動的にグラフが生成されるため非常に便利です。多くの就活支援サイトでダウンロード可能で、たとえば「offerbox.jp」では、すぐに使えるテンプレートが用意されています。
出典:OfferBox(オファーボックス) | スカウト型の就活サイト
PowerPoint形式のテンプレート
PowerPoint形式のテンプレートも、グラフや図形を自由に編集できるため人気があります。グラフの枠組みがすでに用意されており、スライド上で直感的に点や線を追加できるのが特徴です。
プレゼンテーション資料としてそのまま活用できるため、面接や説明会での自己PRにも便利です。
Word形式やPDF形式のテンプレート
WordやPDF形式のテンプレートは、印刷して手書きで記入する場合に最適です。グラフの枠組みがプリントアウトされており、自由に書き込めるため、パソコンが苦手な方や、手書きでじっくり考えたい方におすすめです。
手書き用テンプレートは、就活市場などでも提供されており、印刷してすぐに使用できます。
出典:【テンプレート付き】モチベーショングラフを使った自己分析の方法を徹底解説!【新卒就活生向け】|就活市場
その他のテンプレート
Googleスプレッドシート用のテンプレートも多く配布されており、クラウド上で作業できるため、スマートフォンやタブレットからも編集が可能です。
どのテンプレートも、無料でダウンロードできるため、自分の使いやすい形式を選んで活用しましょう。
おすすめのオンライン作成ツール
モチベーショングラフを作成できるオンライン作成ツールも多数存在します。これらのツールを使えば、パソコンやスマートフォンからどこでも作業でき、データの保存や共有も簡単です。
Googleスプレッドシート
Googleスプレッドシートは、Excelと同様にグラフ作成機能が充実しており、テンプレートを活用すれば短時間でモチベーショングラフを作成できます。
A列に年齢や時期、B列にモチベーションの数値を入力し、「グラフを作成」ボタンを押すだけで自動的にグラフが生成されます。クラウド上で作業できるため、複数デバイスからの編集や、他者との共有も容易です。
オンライン自己分析ツール
一部の就活支援サイトやキャリア支援サービスでは、モチベーショングラフ専用のオンラインツールが用意されています。
これらのツールは、画面の指示に従って出来事や感情を入力していくだけで、自動的にグラフが作成されるため、初心者にもおすすめです。
また、作成したグラフはPDFでダウンロードしたり、画面キャプチャで保存したりできるため、エントリーシートや面接資料として活用できます。
その他の便利なツール
PowerPoint OnlineやCanvaなどのオンラインツールも、グラフや図形を自由に編集できるため、モチベーショングラフの作成に適しています。
これらのツールは、テンプレートが豊富で、デザイン性の高いグラフを簡単に作れるのが特徴です。
モチベーショングラフの活用法

就職活動での提出方法や面接での自己PRへの活用、キャリア選択における価値観の分析など、具体的な活用シーンとポイントを解説します。
就職活動における提出方法とポイント
提出方法と形式の確認
就職活動において、モチベーショングラフの提出を求められるケースが増えています。提出方法としては、エントリーシート(ES)や履歴書の添付資料としてPDFや画像ファイルでアップロードする場合や、面接時にプリントアウトして持参する場合があります。まず、企業ごとの指示に従い、指定された形式やサイズで作成し、データ化・印刷して準備しましょう。
見やすさと内容の明確さを重視
提出にあたっては、グラフの見やすさと内容の明確さが重要です。モチベーションの変化が一目でわかるように、軸や曲線をしっかり描き、各ポイントには出来事や感情を簡潔に記入します。グラフはシンプルかつ丁寧に仕上げ、余計な装飾は避けましょう。また、グラフ以外にグラフの読み方や、特に印象的な出来事の解説などの補足説明文を添えると、採用担当者に伝わりやすくなります。
ありのままを表現する
提出ポイントとしては、自分の価値観や成長過程を正直に表現することが大切です。就活でアピールしたい内容だけを強調したり、自分をよく見せようとするのではなく、ありのままの自分をグラフに反映させましょう。これにより、企業は応募者の本質的な強みや適性をより深く理解できるため、ミスマッチの防止にもつながります。
面接時の自己PRに活用する方法
-
グラフを自己PRの根拠にする
面接時は、モチベーショングラフの「山」や「谷」となった出来事を中心に、自分の成長や価値観の変化を具体的に説明します。「なぜこの時期にモチベーションが高まったのか」「どんな経験が自分に影響を与えたのか」を語ることで、説得力のある自己PRが可能です。 -
具体的なエピソードで強みをアピール
たとえば、「部活動で困難を乗り越えた経験が自信となり、挑戦する姿勢が身についた」など、出来事と感情・学びをセットで伝えると、面接官に納得感を与えられます。 -
グラフ全体で自分の傾向をまとめる
グラフ全体を通して、自分の強みや弱み、働きがいを感じるポイントを整理し、志望企業や職種にどう活かせるかを説明しましょう。 -
論理的かつ具体的な自己表現に
モチベーショングラフを活用することで、自己PRや志望動機が具体性と論理性を持ち、面接官にとって納得感のあるアピールになります。 -
ありのままを伝える姿勢が重要
自分を良く見せようとせず、正直な経験や感情も含めて語ることで、本質的な強みや適性を伝えられます。
キャリア選択における価値観の分析
モチベーショングラフで価値観・働きがいを分析する
モチベーショングラフは、キャリア選択の際に自分の価値観や働きがいの源泉を分析するうえで非常に役立ちます。
グラフの「山」となった出来事や、モチベーションが高まった経験を振り返ることで、「自分がどんな環境や役割で力を発揮できるのか」「どんな課題に取り組みたいのか」が明確になります。
たとえば、チームで目標を達成した経験や、新しいことに挑戦した経験がモチベーションの山になっている場合、協働や挑戦を重視する職場環境が自分に合っていると判断できます。逆に、モチベーションが下がった出来事からは、苦手なことや避けたい状況も見えてきます。
キャリア選択の軸を定め、ミスマッチを防ぐ
モチベーショングラフを通じて自分の価値観や働きがいを分析し、キャリア選択の軸にすることができます。自己分析を深めることで、自分に合った企業や職種を見つけやすくなり、長期的に満足度の高いキャリアを築くことが可能です。
注意点とよくある質問

モチベーショングラフが書けない原因や対策、作成時の注意点、成功事例と失敗事例の比較を通じて、効果的な作成のためのポイントをまとめます。
モチベーショングラフが書けない理由とその対策
書けない理由とよくある悩み
モチベーショングラフが書けない理由として多いのは、「思い出せる出来事が少ない」「どこから手をつけていいか分からない」「モチベーションの高低が判断しづらい」といった悩みです。特に、過去の出来事をすべて詳細に思い出すのは難しく、つい「特別な出来事がない」と感じてしまうこともあります。
大きな出来事から始めてみる
対策としては、まずは大きな出来事だけをピックアップし、細かい部分は後から追加していく方法が有効です。たとえば、小学校・中学校・高校・大学など、区切りごとに印象的な出来事をリストアップし、その時の感情や行動を簡単に書き出します。また、家族や友人に当時のことを聞いてみるのも、記憶を掘り起こす良いきっかけになります。
モチベーションの高低は直感でOK
さらに、「モチベーションの高低」についても、厳密に数値化しようとせず、直感的に「やる気が高かった」「やる気が低かった」と判断しても構いません。最初はざっくりとグラフを作成し、後から細かく修正していくことで、無理なく自己分析を進めることができます。
グラフ作成時の注意すべき点
ありのままを書き出すことの重要性
モチベーショングラフを作成する際は、いくつか注意すべきポイントがあります。まず、出来事や感情を「ありのまま」に書き出すことが大切です。自分をよく見せようとせず、正直に自分の心の動きを表現しましょう。これにより、本当の自分の強みや弱み、価値観が見えてきます。
些細な出来事や心情も丁寧に記録
次に、モチベーションを左右する原因となった出来事は、できるだけ多く思い出して記載しましょう。些細な出来事でも、自分の気持ちに影響を与えたものは積極的に書き込むことで、より詳細な自己分析が可能になります。
グラフ作成は手段、深掘りが本質
また、グラフ作成に時間をかけすぎないようにしましょう。グラフ自体はあくまで自己分析のツールであり、重要なのはグラフを書いた後の「深掘り」や「言語化」です。グラフが完成したら、なぜモチベーションが上がったのか、下がったのかをさらに掘り下げて考えましょう。
成功事例と失敗事例の比較
成功事例:深掘りと言語化がカギ
- 自分の強みや価値観、働きがいを具体的なエピソードとともに明確に言語化できている。
- 例:「部活動でのリーダー経験が自信につながり、その後も積極的に挑戦する姿勢が身についた」など、出来事・感情・学びをセットで説明できる。
- コーチングや第三者の意見を取り入れ、自己分析の精度を高めているケースも多い。
- グラフから過去の成功体験や挫折を分析し、キャリア選択の軸を見つけることができている。
失敗事例:表面的な記述と自己完結
- 出来事や感情の記載が表面的で、モチベーションの高低の理由が曖昧なままになっている。
- 例:「部活で何となくやる気が出なかった」など、原因や背景の掘り下げが不足している。
- 自分だけで完結させ、周囲の意見や客観的な視点を取り入れないことで、自己分析が浅くなりやすい。
ポイント:深掘りと客観性で自己分析の質を高める
- 成功事例では「深掘り」と「言語化」、そして第三者の意見を活用することが共通しています。
- 表面的な記述や自己完結型の分析では、十分な自己理解やキャリア設計につながりません。
- まずは自分の経験や感情をしっかり掘り下げ、必要に応じて他者の意見も取り入れることが、モチベーショングラフを活用した自己分析の成功につながります。
モチベーショングラフの未来と展望

社会人や学生にとっての利点や今後の発展可能性について解説し、モチベーショングラフの将来的な役割や活用の広がりを展望します。
社会人や学生にとっての利点
モチベーショングラフは、社会人にとっても学生にとっても大きな利点があります。まず、自分のモチベーションが上下した経験や感情を可視化することで、価値観や働きがいの源泉、強み・弱みが明確になります。
これにより、就職活動の際に、自分に合った業界や職種を選びやすくなり、ミスマッチを防ぐことができます。また、モチベーショングラフを通じて自己理解が深まることで、自信を持って自己PRや面接に臨めるようになり、仕事や学業でのパフォーマンス向上にもつながります。
チームや組織との関わりにおいても、自分の特性を活かした貢献が可能となり、より良い人間関係や職場環境の構築にも役立ちます。
今後の発展可能性について
モチベーショングラフは、今後さらに多様な場面で活用される可能性があります。デジタルツールやAI技術の発展により、より簡単にグラフを作成・分析できる環境が整いつつあり、個人の自己分析だけでなく、企業の人材育成や組織マネジメントにも応用が広がっています。
また、チームや組織単位でモチベーショングラフを共有し、個々の特性に合わせた業務配分やサポート体制の構築にも活用されています。今後は、キャリア開発やワークライフバランスの最適化、さらには教育現場やメンタルヘルス対策など、幅広い分野での応用が期待されています。