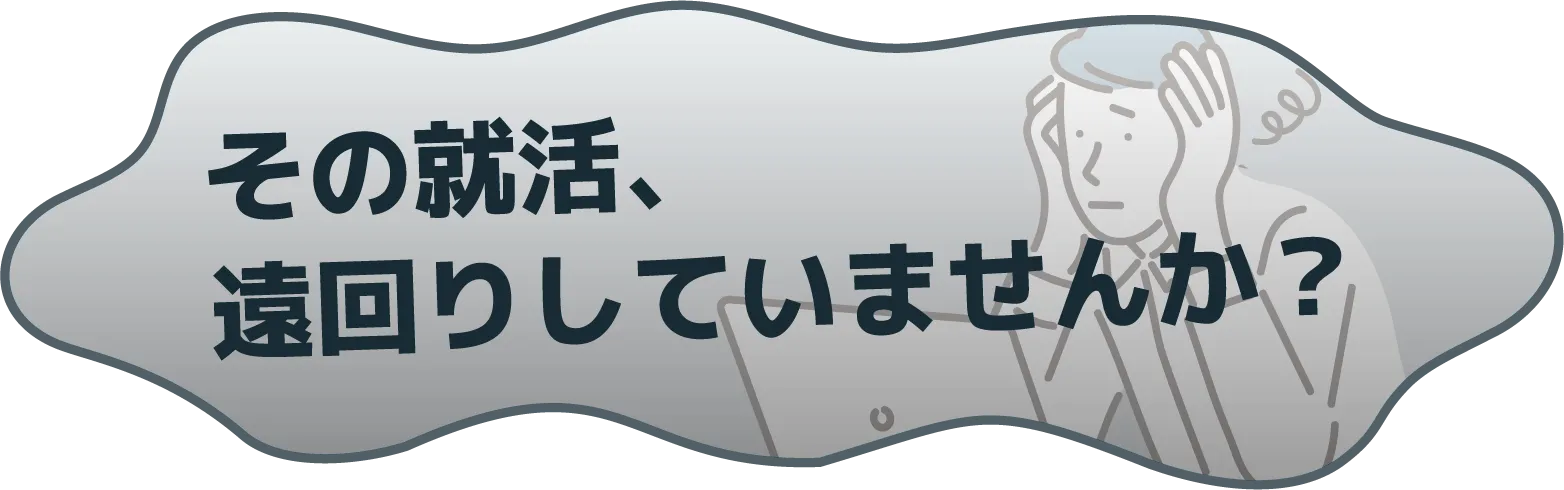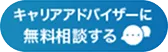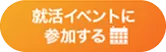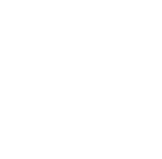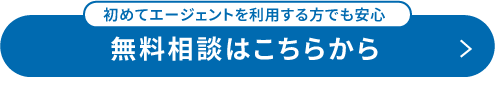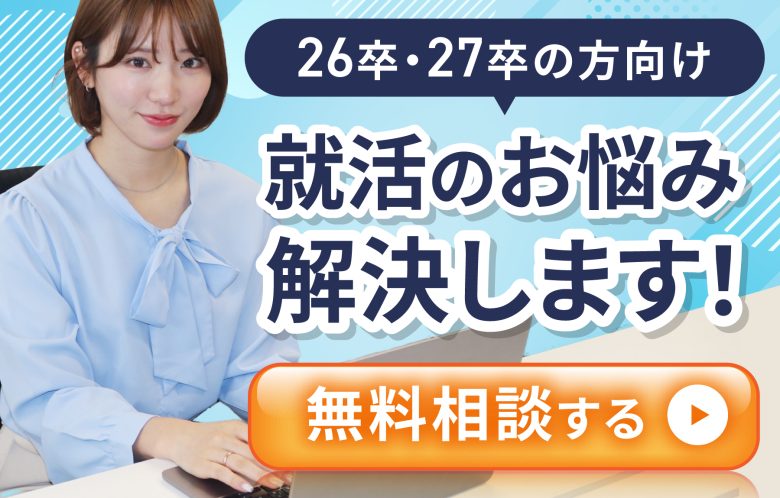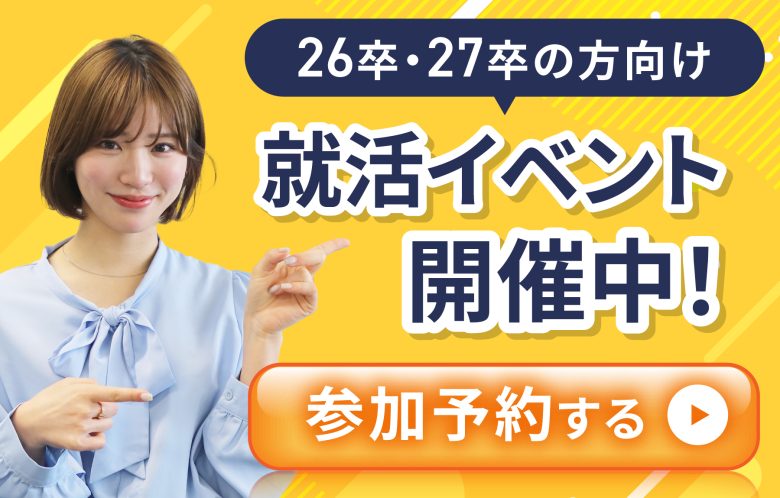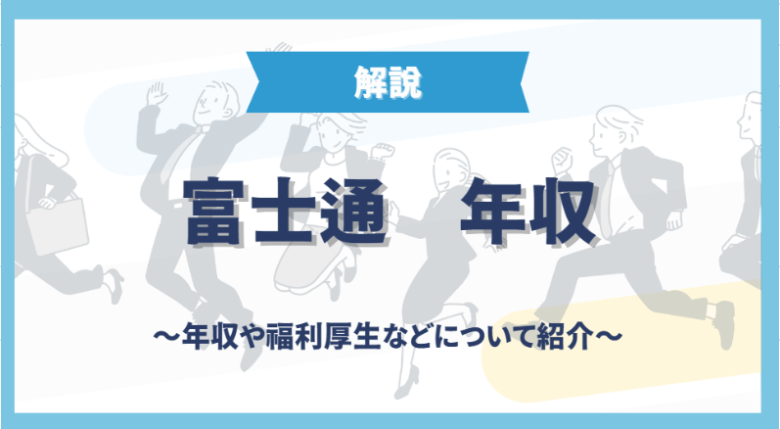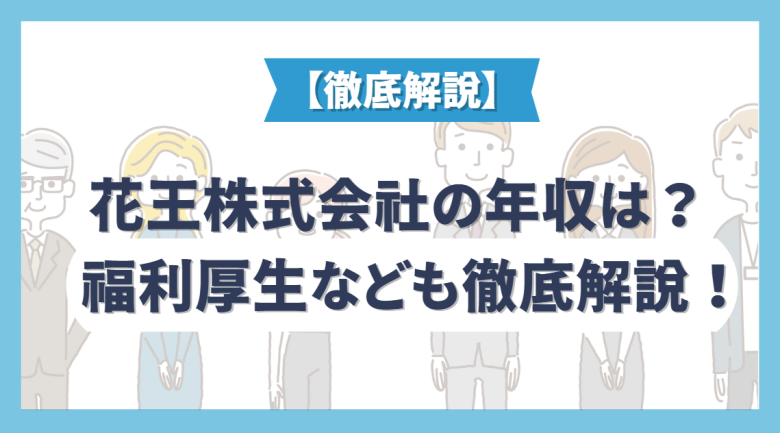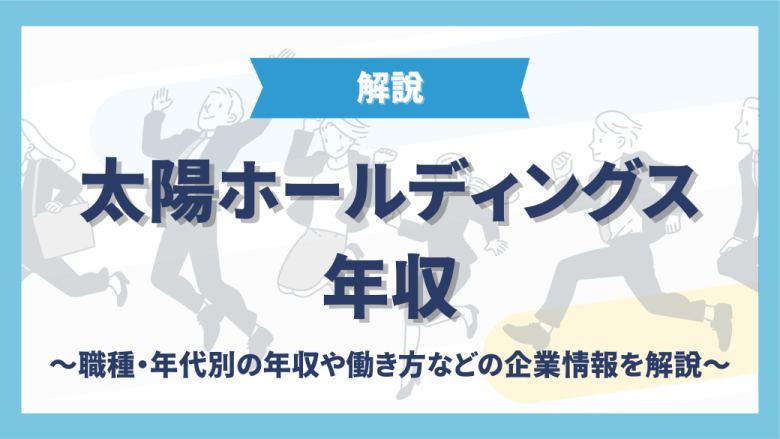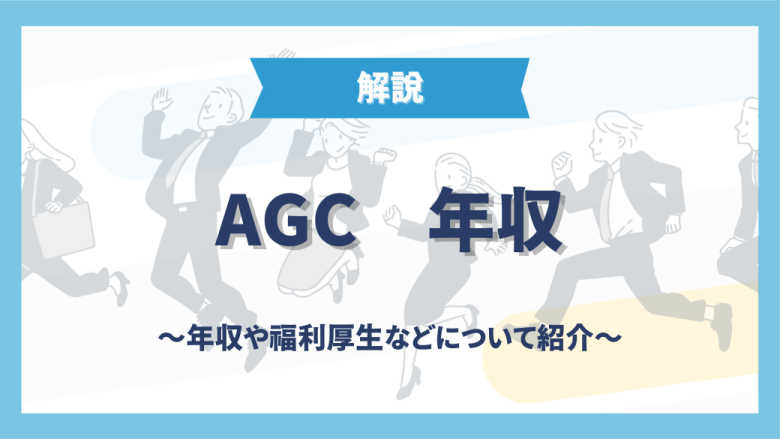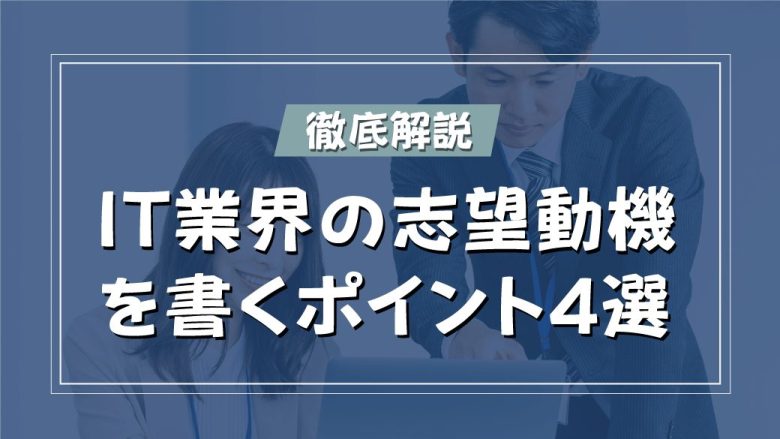通年採用とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説!
2025.07.17 更新


監修者
熊谷 直紀
監修者熊谷 直紀
横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。
2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。
内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。
通年採用が就職活動の新たな選択肢として注目を集めています。従来の新卒一括採用との違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説し、あなたのキャリアプランに最適な採用形式を見つけるお手伝いをします。
大手からベンチャーまで
内定獲得を徹底サポート!!
就活のプロであるキャリアアドバイザーが1対1で直接面談
 入社実績15,000名以上※1
入社実績15,000名以上※1 満足度94%※2
満足度94%※2 最短1週間内定※3
最短1週間内定※3

新卒一括採用と通年採用の違い
新卒採用の方法には「新卒一括採用」と「通年採用」の2つの手法があります。ここからは、それぞれの特徴や違いについて詳しく見ていきます。
新卒一括採用
一般的に就職活動といえば、新卒一括採用を指すことが多く、日本独自の採用方式として広く知られています。この手法では、毎年決まった時期に大学や専門学校などを卒業予定の新卒学生を対象に、一斉に採用選考を実施し、合格者を同じタイミングで入社させるのが特徴です。
スケジュールとしては、3月に企業へのエントリーが始まり、6月から本格的な選考がスタートします。その後、内定を経て、翌年4月に新入社員として一斉に入社します。この流れは多くの日本企業で長年にわたり採用されており、学生にとっても企業にとっても「4月入社」が一つの節目となっています。
通年採用
一方で通年採用は、特定の時期に限らず、企業が必要なタイミングで新卒・中途を問わず採用活動を実施する仕組みです。通年採用では採用活動の時期や期間が限定されていません。
入社時期についても、4月や9月などに限定されず、企業と応募者の都合に合わせて柔軟に決定できます。そのため、学生や転職希望者は自分の状況や希望に合わせて応募でき、留学やインターンシップ、研究活動など多様な経験を積みやすい環境になっています。
海外では「通年採用」が主流です。日本でも近年、グローバル化や多様な人材確保の必要性から、通年採用を導入する企業が増えてきましたが、依然として新卒一括採用が根強く残っています。
通年採用を導入することで、企業は新規事業の展開や既存チームの増員、欠員補充など、必要に応じて求める人材をタイムリーに確保できるようになります。この柔軟性が、グローバル化や人材の多様化が進む現代の採用市場で注目されている理由の一つです。
通年採用をする背景
通年採用が注目される背景には、人材不足の深刻化と人材獲得競争の激化があります。日本では少子高齢化が進み、労働人口が減少しているため、企業は新卒一括採用だけでは十分な人材を確保できなくなっています。このため、第二新卒や既卒者、留学生、海外大学卒業者など、多様な人材を幅広く採用できる通年採用の導入が進んでいます。
また、日本の大学と海外の大学では卒業時期が異なるため、グローバル人材や留学生を確保するには、時期を限定しない採用活動が必要です。さらに、事業環境の変化が激しい現代において、企業は必要なタイミングで柔軟に人材を補強する必要があり、通年採用がそのニーズに合致しています。
加えて、働き方やキャリア観の多様化、副業の容認、終身雇用・年功序列からの脱却といった社会的な変化も、通年採用が注目される理由となっています。こうした背景から、通年採用は今後ますます広がっていくと考えられています。
通年採用のメリット
通年採用には、企業側・学生側の双方にさまざまなメリットがあります。ここからは、通年採用のメリットについて、企業側と学生側それぞれの視点から詳しく説明します。
企業側のメリット
企業が採用活動を行う背景には、経営戦略の実現や組織の活性化、事業の成長に必要な人材の確保など、さまざまな目的があります。こうした目的を達成するために、採用活動には企業側にとって多くのメリットが存在します。
事業の変化や拡大に柔軟に対応できる
事業の拡大や新規プロジェクトの立ち上げ、急な人員不足など、企業活動には予測できない変化がつきものです。通年採用を導入することで、こうした変化に合わせて必要なタイミングで人材を確保できるため、事業戦略の柔軟な実行が可能になります。
従来の新卒一括採用では、特定の時期に集中して採用活動を行うため、タイミングが合わない場合は優秀な人材を逃してしまうこともありましたが、通年採用であれば年間を通じて多様な人材にアプローチできる点が大きな強みです。この柔軟性により、企業は変化する経営環境や人材ニーズに迅速に対応し、競争力を維持・向上させることができます。
留学生・既卒者・第二新卒など、多様な人材を採用しやすい
従来の新卒一括採用ではカバーしきれなかった多様な人材を受け入れやすい仕組みです。たとえば、海外の大学を卒業した留学生や、卒業後に就職活動を始めた既卒者、社会人経験を持つ第二新卒など、さまざまなバックグラウンドを持つ人材が対象となります。年間を通じて採用活動を行うことで、求職者との接点や応募機会が増え、新卒一括採用では出会いにくかった人材とも出会える可能性が高まります。
また、活動期間に制約がないため、応募者の幅が広がり、企業は自社に合った多様な価値観やスキルを持つ人材を確保しやすくなります。グローバル化が進む現代社会では、こうした多様な人材の受け入れが企業の競争力向上や組織の活性化、イノベーションの創出にもつながります。通年採用は、企業が幅広い人材プールから優秀な人材を見つけるチャンスを増やすだけでなく、組織の多様性を高める重要な手法となっています。
応募者一人ひとりとじっくり向き合えるためミスマッチが減る
通年採用では、新卒一括採用のように短期間で大量の応募者を同時に選考する必要がありません。そのため、採用担当者が一人ひとりの応募者とじっくり向き合い、適性や志向、スキルなどを丁寧に見極めることができます。このように時間的な余裕を持って選考を進められるため、企業と応募者の間で期待値のズレが生じにくくなり、入社後のミスマッチや早期離職のリスクを大幅に減らすことが可能です。結果として、長期的な人材定着にもつながり、企業にとっても応募者にとっても満足度の高い採用が実現しやすくなります。
内定辞退や採用計画の変更にも柔軟に対応できる
新卒一括採用では、年に一度の採用活動に依存しているため、内定辞退者が多発した場合や事業計画の変更があった際に、追加で人材を確保するのが難しくなります。採用活動の時期が限られているため、辞退者が出ると予定していた採用数に満たなくなるリスクが高まり、企業は内定者のフォローや採用計画の見直しに多大な労力を要します。
一方で、通年採用であれば、内定辞退や急な人員不足が発生した場合でも、すぐに新たな採用活動を開始できるため、採用計画の変更や人員補充にも柔軟に対応することが可能です。年間を通じて採用活動を行っているため、補完計画を立てやすく、必要な人材をタイムリーに確保できます。この柔軟性により、企業の人材戦略におけるリスクを大幅に軽減できる点が、通年採用の大きな強みとなっています。
学生側のメリット
もちろん企業側だけではなく、学生側にも通年採用には多くのメリットがあります。自分のペースで就職活動を進められることや、より多くの企業に応募できること、そしてじっくりと準備をして選考に臨めることなど、学生にとっても大きな利点があります。
自分のキャリアプランに合わせて就職活動ができる
通年採用では、就職活動の時期が決まっていないため、学生は自分のキャリアプランやライフスタイルに合わせて活動を進めることができます。たとえば、留学や研究、ボランティアなどに力を入れたい場合でも、それらの活動が終わってからじっくりと就職活動に取り組むことが可能です。
新卒一括採用のように短期間で多くの企業の選考を受ける必要がなく、自己分析や企業研究、面接対策などの準備に十分な時間をかけることができます。このため、自分に合った企業を納得して選ぶことができ、入社後のミスマッチを減らせる点が大きなメリットです。
卒業後や既卒でも応募でき、就職のチャンスが広がる
通年採用は新卒だけでなく、卒業後や既卒者、第二新卒なども応募の対象となる柔軟な採用方式です。
そのため、卒業後に進路を再検討したい場合や、一度社会に出てから新たなキャリアに挑戦したい場合でも、就職のチャンスを失うことがありません。エントリーのタイミングが限定されていないため、自分の状況や希望するタイミングに合わせて応募でき、キャリアの選択肢が大きく広がります。このように、通年採用は多様なバックグラウンドを持つ人にとって、より多くの可能性に挑戦できる点が大きな特徴です。
ミスマッチが減る可能性がある
通年採用では、年間を通じて複数の企業や職種に応募できるため、学生は自分に合った企業をじっくりと選ぶことができます。新卒一括採用のように短期間で内定を決める必要がないため、企業研究や自己分析に十分な時間をかけられ、納得したうえで就職先を決定することが可能です。その結果、企業との相互理解が深まり、入社後のミスマッチや早期離職のリスクを減らせる点が大きなメリットです。
通年採用のデメリット
通年採用には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。企業や学生が通年採用を検討する際には、こうした課題やリスクについても理解しておくことが重要です。
企業側のデメリット
企業側が導入する際にはいくつかの注意点や課題も存在します。導入前にデメリットについても十分に理解しておくことが重要です。
採用担当者の負担や業務量が大きくなりやすい
応募者のエントリーや選考が年間を通じて発生するため、採用担当者は常に対応を求められる状況になります。これまでの新卒一括採用のように特定の時期だけ集中して採用活動を行うのではなく、1年中採用業務が続くため、他の業務と兼任している担当者にとっては特に負担が大きくなります。その結果、担当者の疲労や残業の増加、業務効率の低下が懸念され、企業によっては専門チームの設置や業務分担の見直しが必要となる場合もあります。
一斉研修や組織文化の浸透が難しくなる
入社時期がバラバラになるため、従来のように同期を集めて一斉に研修を実施することが難しくなります。その結果、研修の効率が下がったり、社員同士の一体感や組織文化の共有がしづらくなるケースが生じます。新入社員が孤立しやすくなるほか、教育体制の見直しや個別対応の負担が増えるなど、組織運営上の課題が発生する可能性もあります。このため、通年採用を導入する際は、研修や組織文化の浸透方法について工夫が求められます。
学生側のデメリット
もちろん企業側だけではなく、学生側にも通年採用にはデメリットがあります。採用基準が高くなりやすいことや、就職活動が長期化しやすいこと、効率的な情報収集が難しいことなど、学生が注意すべき点も存在します。これらについて説明します。
情報収集やスケジュール管理が難しくなる
通年採用では、企業ごとに選考の開始時期や応募締切が異なるため、学生自身が積極的に情報を収集し、各社のスケジュールを的確に管理する必要があります。エントリーや面接の日程が重なることもあるため、効率的な就職活動を行うには、高いスケジュール管理能力と情報収集力が求められます。自ら明確な計画を立て、全体の進捗を把握しながら活動を進めることが、成功の鍵となります。
同期が少なくなり、入社後の人間関係に不安を感じやすい
入社時期が分散するため、同じタイミングで入社する同期が少なくなります。その結果、入社直後の人間関係の構築が難しくなったり、従来のような一斉研修が受けられない場合があります。同期とのつながりや相談相手が減ることで、職場に馴染むまでに時間がかかったり、孤立感を感じやすいなどの不安を持つ学生も少なくありません。このため、入社後のサポート体制やコミュニケーション機会の工夫が必要となります。
精神的・時間的な負担が増える場合がある
就職活動の期間が長期化する傾向があり、学生は常に情報収集や応募準備を続ける必要があります。そのため、学業やアルバイト、プライベートとの両立が難しくなりやすく、「いつまで就活を続ければよいのか」といった精神的なプレッシャーを感じることもあります。また、活動期間が長い分、モチベーションの維持や自己管理が課題となり、計画的に進めないと負担が増大しやすい点がデメリットです。
選考の難易度が高くなる場合がある
新卒だけでなく、既卒や第二新卒、社会人経験者も応募対象となるため、選考の競争相手が多様になります。企業は即戦力や実務経験を持つ応募者を重視する傾向があり、新卒学生はこうした経験者と同じ土俵で評価されるケースが増えます。そのため、従来の新卒一括採用よりも選考基準が高くなり、自己PRや面接対策、実践的なスキルの準備がより重要となります。結果として、選考突破のハードルが高く感じられる場合が多いのが通年採用の特徴です。
両者の特徴をより分かりやすく比較できるよう、主な違いを表にまとめました。
| 比較項目 | 新卒一括採用 | 通年採用 |
|---|---|---|
| 採用時期 | 年1回(主に春)。3月に採用の広報活動が解禁、6月に採用選考が解禁など、決まったスケジュールで実施。 | 年間を通じて随時。企業が必要なタイミングで採用活動を開始し、時期に制約がない。 |
| 対象者 | 新卒学生(卒業予定者)のみ。既卒や中途は基本的に対象外。 | 新卒・既卒・第二新卒・中途・留学生・外国人など多様な人材が対象。 |
| 入社時期 | 4月(または秋)に一斉入社。卒業時期に合わせて同期で入社するのが一般的。 | 企業や応募者の都合に合わせて柔軟に決定する。 |
| 採用の柔軟性 | スケジュールや対象者が限定されているため、急な人員補充や多様な人材の受け入れが難しい。 | 必要なときに必要な人材を採用でき、状況に応じた人員補充や多様な人材の採用がしやすい。 |
| 人材確保の機会 | 限定的。年1回の採用機会に依存するため、内定辞退などがあると補充が難しい。 | 継続的。年間を通して採用できるため、内定辞退や急な人員不足にも柔軟に対応できる。 |
| 選考方法・人数 | 一斉に大量採用。短期間で多くの応募者を同時に選考する。 | 個別に少人数ずつ採用。1人ひとりをじっくり見極めて選考できる。 |
| 応募期間 | 数ヶ月に限定。エントリーや応募の時期が決まっている。 | 通年で受付。就活準備が整ったタイミングでいつでも応募できる。 |
| 対応できる人材 | 主に将来性やポテンシャルを重視。長期的な育成を前提とする。 | 即戦力や特定スキルを持つ人材、従来採用できなかった層にも対応。 |
通年採用を導入する企業の共通点・傾向
通年採用を導入している企業には、いくつか共通した特徴や傾向が見られます。従来の新卒一括採用とは異なり、企業規模や業種を問わず、柔軟な働き方や多様な人材の受け入れを重視する企業が増えているのが現状です。次に、通年採用を導入する企業の共通点や傾向について説明します。
グローバル展開を進める企業や、人材流動性の高い業界
グローバル展開を積極的に進める企業や、IT業界、外資系企業など、人材の流動性が高く即戦力の確保が重視される業界では、通年採用の導入が特に進んでいます。これらの企業では、海外拠点や多国籍チームでの業務が多く、国際的な人材や多様なバックグラウンドを持つ人材を柔軟に受け入れる必要があります。
また、企業が職務内容を明確に定義し、その遂行能力に基づいて評価や報酬を決定する「ジョブ型雇用」や、プロジェクト単位での採用が一般的なことから、年間を通じて必要なタイミングで人材を確保できる通年採用は非常に適しています。こうした背景から、通年採用はグローバルな競争力の強化や、多様な人材の活用を目指す企業にとって重要な採用手法といえます。
新規事業や急成長中の企業、人材不足が深刻な企業
新規事業を展開している企業や急成長中のスタートアップ、人材不足が深刻な業界が多い傾向があります。これらの企業は、事業環境の変化や組織拡大に迅速に対応する必要があり、従来の新卒一括採用ではタイミングが合わず、必要な人材を逃してしまうリスクが高まります。
通年採用を取り入れることで、こうした企業は事業の成長スピードや新規プロジェクトの立ち上げに合わせて柔軟に人材を補強できるようになります。実際に、IT業界やベンチャー企業、通信・インターネットサービス大手など、変化の激しい業界や人材確保が急務な企業で導入が進んでおり、競争力の維持や事業推進に大きく寄与しています。
通年採用をしている企業に合う人材の特徴
通年採用を導入する企業の多様性や柔軟性、グローバル志向にフィットしやすく、組織のイノベーションや成長を支える存在として期待されています。
通年採用を導入している企業に合う人材の特徴は、以下の点に集約されます。
実力主義・即戦力志向
実力主義・即戦力志向が強く、入社直後から成果を出せるスキルや実務経験、専門性を持つ人材が特に重視されます。即戦力人材は、業務に必要な知識や技術をすでに備えており、短期間で現場に適応し、具体的な成果や実績を示せることが求められます。
また、自ら学び続ける姿勢や、変化の激しいビジネス環境やプロジェクト単位の業務に柔軟に対応できる力も評価されやすい傾向です。問題発見力や改善提案力、周囲と協力しながら課題を解決する能力も重要視され、単なるスキル保有だけでなく「実務で活かしてきた経験」が重視されます。このような環境では、即戦力人材の確保が企業の成長や競争力強化に直結しています。
変化への適応力と柔軟性
事業環境の変化や組織の拡大に迅速に対応するためには、変化への適応力と柔軟性を持つ人材が不可欠です。こうした人材は、新しい働き方や制度を前向きに受け入れ、リモートワークやフレックスタイムなど多様な勤務形態にもスムーズに順応できます。フレックスタイム制度や在宅勤務の導入によって、従業員は自分のライフスタイルや生活リズムに合わせて働くことが可能となり、ワークライフバランスの向上やストレス軽減にもつながります。
また、柔軟な働き方を重視する企業では、従業員一人ひとりのニーズに応じた労働条件を提供し、多様な人材の活躍を促進しています。このような環境で求められるのは、状況に応じて自ら考え行動できる自律性と、変化を楽しみながら成長できる前向きな姿勢です。
コミュニケーション力と協調性
異なる意見や価値観を持つ相手の考えを尊重し、自分の意見をわかりやすく伝える力、そして相手の意図や背景を汲み取る力が求められます。グローバルなビジネス環境では、語学力や異文化理解も含めて、社内外の多様な関係者と円滑に連携できることが理想とされています。
また、協調性とは、利害や立場の異なる人とも譲り合い、妥協点を見つけながら共通の目標に向かって協力できる力です。こうした資質を持つ人材は、チームワークを高め、組織の生産性や創造性の向上に大きく貢献します。グローバル化が進む現代の職場では、コミュニケーション力と協調性は不可欠なスキルといえるでしょう。
自律性・主体性
個人のキャリアやライフスタイルに合わせて働くことができるため、自律性や主体性が非常に重視されます。自ら目標を設定し、計画的に行動できる人材は、企業が求める多様な働き方やキャリアパスに柔軟に対応しやすいです。自分の強みや専門性を理解し、それを活かして組織の成長や目標達成に積極的に貢献できる姿勢が評価されます。
また、通年採用を導入する企業は、学年や新卒・中途、国籍を問わず、誰もが主体的に応募できる環境を整えているため、自分自身でキャリアを切り拓きたいという意欲や、納得のいく将来像を描く力も重要です。このような自律性・主体性を持つ人材は、変化の激しいビジネス環境でも自ら成長し続け、企業の新たな価値創出に貢献できると期待されています。
通年採用での活動と選考の流れ
通年採用では、企業ごとに選考の開始時期や締切が異なり、年間を通じてエントリーや選考が行われます。学生は自分のタイミングで応募でき、各社の選考フローに沿って書類選考や面接、適性検査などを受けます。新卒一括採用のような短期集中型ではなく、複数の企業の選考が同時並行で進むことも多いため、スケジュール管理が非常に重要です。
また、通年採用では企業ごとに選考回数や内容が異なり、選考期間が短い場合もあるため、事前の企業研究や自己分析、応募書類の準備、面接対策をしっかり行う必要があります。情報収集を怠ると、エントリーや面接の日程が重なり、応募機会を逃すリスクもあります。選考が長期化する場合もあるため、就職活動に集中しすぎず、適度に息抜きをしながら計画的に進めることが大切です。
このように、通年採用では自分のペースで活動できる一方で、情報収集力やスケジュール管理能力がこれまで以上に求められます。企業ごとに異なる選考フローに柔軟に対応し、それぞれに合わせた対策を講じることが、納得のいく就職活動につながります。
実力・成果主義の評価制度
通年採用を導入する企業では、学歴や年齢、勤続年数よりも、個人のスキルや実績、実際の業務で出した成果を重視する評価制度が特徴です。年功序列にとらわれず、成果に応じて昇進や昇給の機会が与えられるため、若手社員でも高いパフォーマンスを発揮すれば早期に活躍できる環境が整っています。こうした実力・成果主義の文化は、社員一人ひとりの成長意欲や挑戦心を引き出し、組織全体の生産性向上や競争力強化にもつながります。
丁寧なマッチングと個別対応
通年採用企業は、選考期間に余裕を持たせているため、応募者一人ひとりとじっくり向き合い、スキルや価値観が自社と合うかどうかを丁寧に見極めることを重視しています。面接やインターンシップなどを通じて、個別の強みや志向性を理解し、最適なポジションやキャリアパスを提案する姿勢が特徴です。このような丁寧なマッチングと個別対応により、入社後のミスマッチを減らし、社員の定着率や満足度の向上を実現しています。
情報収集方法
企業ごとに募集時期や選考内容が異なるため、学生は積極的な情報収集が不可欠です。主な方法としては、企業の公式サイトや就職情報サイト、ナビサイトを定期的にチェックし、「通年採用実施中」「随時エントリー受付中」などの記載を確認することが基本です。また、SNSやYouTube、オウンドメディア、メールマガジンなど、企業が発信するさまざまな媒体も活用し、最新の採用情報や社風を把握します。
さらに、大学のキャリアセンターや就職・転職イベント、合同説明会にも積極的に参加することで、企業担当者から直接情報を得たり、一般公開されていない選考情報を入手できる場合があります。OB・OG訪問やインターンシップも、実際の働き方や社内の雰囲気を知るうえで有効です。このように、複数の情報源を組み合わせて活用し、エントリーや面接日程を自分で管理する力が通年採用では求められます。
まとめ
通年採用は、企業と求職者双方にとって柔軟性と多様性をもたらす新しい採用手法として注目されています。グローバル展開を進める企業や人材流動性の高いIT業界、外資系、急成長中のスタートアップなどで導入が進み、即戦力や多様なバックグラウンドを持つ人材の積極的な受け入れが特徴です。
こうした企業に合う人材は、実力主義・即戦力志向、変化への適応力と柔軟性、コミュニケーション力と協調性、自律性・主体性を備えており、多様な働き方やグローバルな環境でも自らの強みを活かし、組織の成長に貢献できることが求められます。
就職活動を考える際は、新卒一括採用だけでなく、通年採用を行っている企業にも目を向けることで、より自分に合った働き方やキャリアの選択肢が広がります。多様な採用形態を知り、自分の強みや希望に合った企業を見つけることが、納得のいく就職活動につながるでしょう。